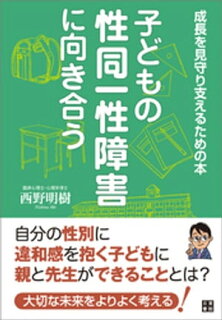「必要が無い」の意味のすれ違い
- いわゆるLGBT理解増進法案「カムアウトする必要が無い社会」
- 「カムアウトしても問題ない社会」ではない「必要が無い社会」とは?
- 「カムアウトしなくてもいい状況を作るよう強要する」意味の岩手県庁ガイドライン
- 「性自認を尊重」する社会で「カムアウトは不要」となると管理権者の意思は…?
- 性的マイノリティの理解増進に寄与する表現、議論の仕方の継続
いわゆるLGBT理解増進法案「カムアウトする必要が無い社会」
いわゆるLGBT理解増進法案として2023年の自民党案が公になりました。
細かい問題点はあるのですが、本稿では本法案の目的としてしばしば語られる表現である「カムアウトする必要が無い社会」という文言について集中的にその注意点を取り上げます。
「カムアウトしても問題ない社会」ではない「必要が無い社会」とは?
「必要が無い」の国語的意味は「必ずしも要しない=求められる場合もあれば求められない場合もある」というものが第一義的のようです。
が、中には「いらない≒求められることは一切無い」の意味で用いている場合もあります。「不要」という表現の場合はこっちの意味が支配的でしょう。
意外と後者の理解も多くみられます。
自民党の「カミングアウトする必要のない社会」って、カミングアウトがゲイリブの流れで生まれたアクションだということをまったく理解してないから出る発言だと思う。「懺悔に近い告白」ぐらいの意味にとってるんじゃないかな。本来「必要ない」なんて言ってはいけないものなのよ。
— 森奈津子 (@MORI_Natsuko) 2016年4月28日
悪気はなくても、「カミングアウトする必要のない社会」っていう表現は「おまえらLGBTは人権を主張するな。隠れてろ」って言ってるようなものだから、もし、わかってなかったのなら、早いところ訂正・謝罪したほうがよい案件。
— 森奈津子 (@MORI_Natsuko) 2016年4月28日
法令用語としては、e-gov法令検索で「必要がない」で検索すると300を超えるヒットがありますが、たとえば許認可の場面の話では「必要がない=求められることは一切無い」の意味です。
また、「必要があると認めたとき」の反対の状況として「必要がないと認める…」と規定されている場合、「必要がない」場合は「それをやってもやらなくてもよい」ではだめという場面もあります。
例:「入院を継続する必要がないと認めるときは、すみやかに、その者を退院させなければならない。」
他方で、「必要がない」とある場合でも「やってもやらなくても問題はない、違法不当の話にはならない」という含意がある場面もあります。
例:「〇〇の必要がないと認める〇〇については、〇〇をしないことができる」「〇〇の必要がない場合においては、この限りでない」のような規定の場合。
こうした疑問が生まれたのは、「カムアウトしても問題ない社会ではなくカムアウトの必要が無い社会」というような言い回しを聞いたからです。
「カムアウトできる社会ではなくてカムアウトの必要がない社会」
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2023年5月20日
って言ってるんで。https://t.co/bvb25NsJvX
たぶんここの「ではなくて」は、より適切な表現としては、の意味合いなんだろうけどさ。標語の説明だから。
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2023年5月20日
(「必要が無い」の意味のブレについては別ツイート参照)
でも、こういう所が利用されてしまうんだよ。という事です。
「カムアウトしなくてもいい状況を作るよう強要する」意味の岩手県庁ガイドライン

「カムアウトする必要が無い社会」という表現は、ややもすると岩手県庁のガイドラインのような『希望者が事情を説明しなくても利用できる体制の整備を』という【施設側への強要】が行われる社会も含意してると解されかねない。
もちろん、岩手県庁ガイドラインは、医療の場面では「業務上性別情報が必要なものの例」として例を挙げています。
しかし、これは「ポジティブリスト方式」であり、ガイドライン全体としてはデフォルトの態度は「不要」というベースがあるということになります。天秤が平衡で一定の場面では求められない、ではなく、特に明言しない限りは「不要」というスタンス。
本来的に性別による振り分けが求められるはずのトイレ・入浴施設・更衣室に関して『希望者が事情を説明しなくても利用できる体制の整備を』などと書いているので、そのように理解するほかない。
いわゆるLGBT理解増進法案の目的が「自治体の暴走に歯止めをかける」ものであると主張されていますが、仮にこのようなガイドラインを許すのであれば、歯止めにはならない。
「一定の場合には原則として求められる」「こういう場合には不要とする」という趣旨が明確にならない限り、「〇〇の必要が無い社会」という言い方は、かなり注意が必要だということ。
性的指向は「個人対個人」
— がんのさとし (@ganno_satoshi) 2023年5月17日
性自認は「個人対社会」
性自認はあくまでも自認。
なので他者に主張するには、
他者、つまり社会の承認が必要。
医療事故防止の観点では、医療チーム全員が妊娠の可能性を瞬時に想定する工夫として、男女の区別は必要です。
この指摘の前半部分は、何も医療という限定的な場面でのみ妥当するものではない。
普遍的な状況で妥当するものです。
例外的に、その者の考える自己の属する性について外部表出することが求められないようにすべき場面があるだけです。
そうでしょう?「その者がどう考えているのかわからないのであらゆる状況に対応できるように準備せよ」なんて、社会を疲弊させるだけです。
例えば「自分は男だが男と風呂に入るのは身体的特徴や心の問題から苦痛だ。個別対応して欲しい」と旅館側に伝えるのが不要なら、外形的には単にワガママでVIP対応しろと言ってることになる。見た目や音で分かるならともかく。
「僕ちゃんの考えてることを社会は察してそれに適した対応をして」なんて、自立した人間のものではない。自己の要求を根拠を持って伝えるコミュニケ―ションが必要。
それを表に出すことで不利益を被ることが無いようにするというのが「カムアウトできる社会」「カムアウトしても問題ない社会」。
もちろん、未成年の児童生徒の場合には積極的な配慮が必要。
「性自認を尊重」する社会で「カムアウトは不要」となると管理権者の意思は…?
「性自認を尊重しましょう」という社会の元で「トイレ・更衣室・入浴施設ですらカムアウトは不要」となるとどういう結果になるかというと「予め男女の別の無いスペースを作る」か「女のスペースに男が入っても許容する」ことになる。
すると、刑法上の建造物侵入罪における「管理権者の意思」が、「それら」を受容してるものとして「法的に」扱われかねない。
こういう社会では現実に存在する人間である管理権者Aさんが「生物学的男性は女性用のトイレ・更衣室・風呂には入れてはいけない」と考えていたとしても、その意思が外部に表出されていなければ、法的には管理権者の意思として「生物学的男性でも性自認が女性であれば特段の反対の意思が示されない限り、女性用のトイレ・更衣室・風呂に入ることを受容している」と判断されるおそれは付きまとう。
流石に刑法上の構成要件該当性判断には影響しない場合であっても、「生物学的男性は女性用のトイレ・更衣室・風呂には入れてはいけない」という扱いが為されている或いはその意思が外部に表出した段階で、活動家らが「この差別主義者が!」と攻撃をしてくることは想像に難くない。
そうした懸念を生じさせるような「カムアウトする必要の無い社会」という文言の使用は慎むべきであり、国会審議をするのであれば、その趣旨が明確化されるべきでしょう。
性的マイノリティの理解増進に寄与する表現、議論の仕方の継続
こうしたベーシックな言葉の意味のレベルで議論が揃ってない場合があり、すれ違いが起こってることが相当数あるのだろうと思われます。
ちょっとした言葉足らずで発せられた「理念」上の言葉を積極的に勘違いさせて、変なガイドラインや条例などが創られる危険がある。岩手県庁のような勘違いが生まれる。
それを言葉で・立法で事前コントロールするのが議員の・国会の仕事であり、事後的な行政側との折衝以前に意識されなければならない。
自民党が特命委員会を作って、法案化を前提にした情報収集、議論をしてなければ、今ほどの知見は得られてなかったように思います。
— Nathan(ねーさん) (@Nathankirinoha) 2023年5月20日
その意味でこの8年間は「無駄」や「切り崩された」ではなく、理解増進に寄与した、と見るべきなのだろうと。 https://t.co/s9m4p9Fhrp
「法案推進者・作成者がこう言ってたから現実の展開や法解釈はその通りになります」
なんて思ってはいけないよ。嘘をついてるかも知れないし、本人らの想像力が欠如してるかも知れないし、立法過程やその後の政策化の間に変質してしまう事はあるからね。
「派遣の雇止め」だって、「5年経ったら無期雇用」という法律ができたら4年目で契約終了するところが多数出たりしたじゃないですか。
そうならないようにコントロール出来る方法の一つが国会審議。
法案修正ができなくとも答弁で立法趣旨が明確になる。附帯決議でも良いでしょう。
本来、LGBTの訓詁学なんて一般国民は知らなくて良い。
標準知識として細かい事を覚える必要はない=不要。
そうせずとも性的マイノリティらへの不当な扱いが無い社会にするのが政治の役目だと思うし、不当な扱いが無い、という以上に、児童生徒らが悩んでるのであればそれへの対応が適切に行える社会であろう、というのも正当。
性的マイノリティとしての(自分がそうであるとの確信を持てなくとも)苦悩を軽減、解消するための社会的な知見の共有はあっても良いと思います。
以上:ランキングバナークリック,はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします