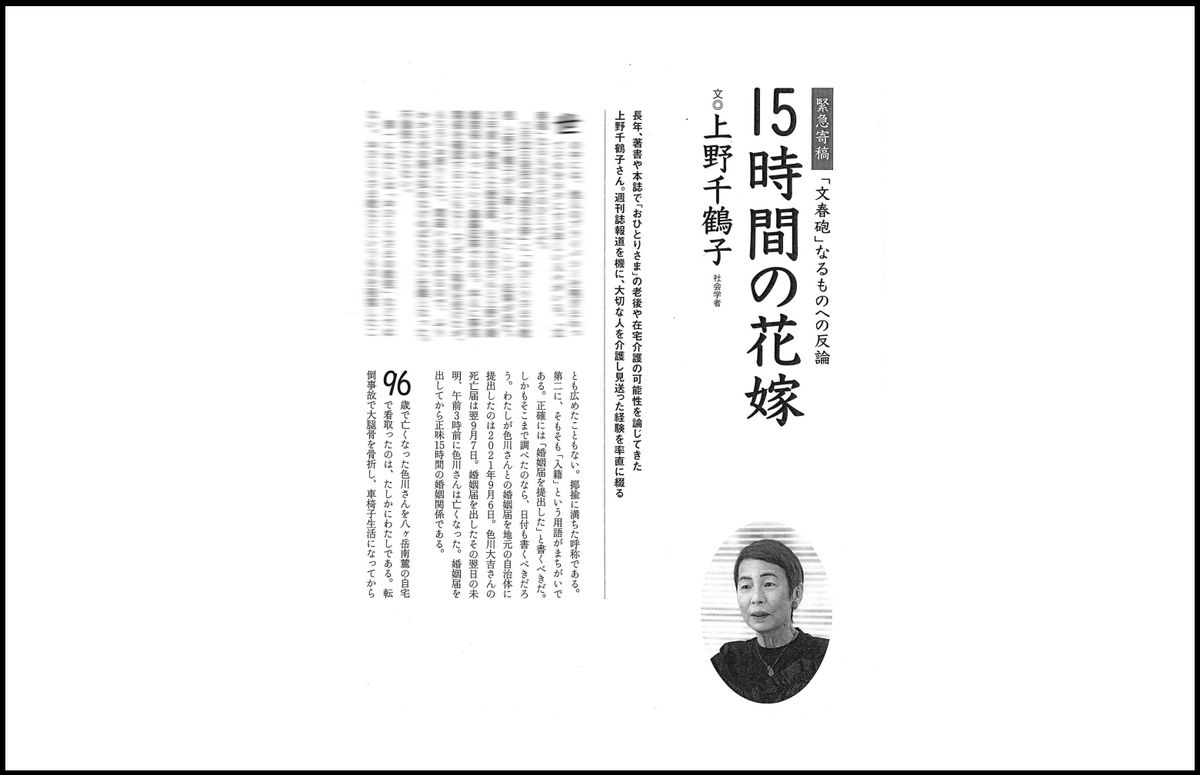
ネットミームの害悪
- 上野千鶴子が色川大吉と入籍の文春報道
- 婦人公論4月号で反論「おひとりさまの教祖ではない」
- 上野名誉教授の「おひとりさま論」の意味:独身を積極推奨していない
- 「上野千鶴子が色川大吉と入籍」は婚姻なのか養子縁組なのか?論
- 法的婚姻関係を偽装する婚姻届の提出=婚姻意思の不存在=無効自由
- 特別縁故者としての上野千鶴子と親族からの婚姻無効訴訟の可能性は?
上野千鶴子が色川大吉と入籍の文春報道
“おひとりさまの教祖”上野千鶴子(74)が入籍していた#週刊文春https://t.co/VsZ3grQY0L
— 週刊文春 (@shukan_bunshun) 2023年2月21日
「文春砲」なる下劣な報道が出た。ふりかかった火の粉は払わなければならない。反論を3月15日発売の『婦人公論』に書いた。興味があれば読めばよい。
— 上野千鶴子 (@ueno_wan) 2023年3月1日
東大名誉教授の上野千鶴子が色川大吉と入籍していたという文春報道があり、上野氏が反論をしていました。
本件については事実誤認に基づく言説が吹き荒れたのでここで整理します。
婦人公論4月号で反論「おひとりさまの教祖ではない」
婦人公論 2023年4月号にて、上野氏はまず「第一にわたくしは「おひとりさまの教祖」どではない。おひとりさま教などというものを発案したことも広めたこともない。揶揄に満ちた呼称である」としています。
これに対しては「おひとりさまの教祖」というのは「揶揄であってその通りの指摘ではない、だから論点逸らしだ」「本人の意思とは関係なくそのように崇める者も居るのだ」というような論調も展開されています。
が、ネット上では上野氏の「おひとりさま論」の意味を明らかに誤解している者で溢れたので、それを知りつつ「ダブスタ」のような批判をするのは「上野千鶴子批判風エンタメ」でしかなく、そちらの方が有害だと思います。
本件に限らずネット上の「上野千鶴子批判」の相当数が、存在しない主張を彼女がしていることにして叩いているという現象が起きています。
上野名誉教授の「おひとりさま論」の意味:独身を積極推奨していない
上野名誉教授はおひとりさまの老後以来、累次の書籍等によって「おひとりさま」となる現代の女性に対してその生き方、心構えを提唱してきました。
ちなみに八木さんはこの記事の中で『おひとりさまの老後』の「内容をまとめると」と要約してくださっています。……「結婚していても子供がいても離婚しても生涯独身でも、長生きすれば、みんな『おひとりさま』になる。最期はみんな同じ『おひとりさま』。離婚も生涯独身もそれぞれハッピーで決して不幸ではない」と。なんて的確な要約でしょう。
上野氏がこのように主張する根拠として
- 男性よりも女性の方が一般的に寿命が長く、現代は高齢化した
- 結婚同居してても「夫と死別した女性」というおひとりさま状態になる
- 現代では婚姻すると世帯分離する慣行が広がっている
- そのため、その人にとっての親世代・子供世代の同居親族が居ない者が多い
このような事情を挙げています。
端的に言えば「おひとりさまの状態になることを積極的に推奨しているわけではない」と言えます。「不可避的に生ずる可能性が高い「おひとりさま」状態に備えよう」、という以上の意味は無い。
巷の「おひとりさま」論批判は、一種のストローマン論法となっている。
彼女の主張が「独身や子なし夫婦や離婚を選択することを結果的に助長した」と言えるかは分からない。なお、上野氏自身は「結婚はセックス契約」と評しています。
「逃げ恥」の契約にセックスが含まれないのは不自然。結婚とはセックス契約なのに。一回当たりのセックスコストを誰が誰に支払うのか?家事と同じくセックスも「愛の労働」、しかも「無償労働」だ。こういう議論はほぼ「不払い労働論」で尽くされている。おぞましい議論だが、現実がおぞましいのだ。
— 上野千鶴子 (@ueno_wan) 2016年12月22日
なお、「この記事」とは産経新聞2014年3/19付けの正論コラムです。上掲の要約の後に以下の記述があります。
【正論】「おひとりさま」の勧めは無責任 高崎経済大学教授・八木秀次(2/4ページ) - 産経ニュース
要するに、最期はみんな「おひとりさま」だから、結婚しなくていい、子供も産まなくていい、離婚も怖くないという主張である。同時に、最期まで子供など頼らずに、「おひとりさま」で在宅し続けることの勧めでもある。
このように理解できてしまうのは、現実の彼女の立場がそういう状況だからだろうか?
「上野千鶴子が色川大吉と入籍」は婚姻なのか養子縁組なのか?論
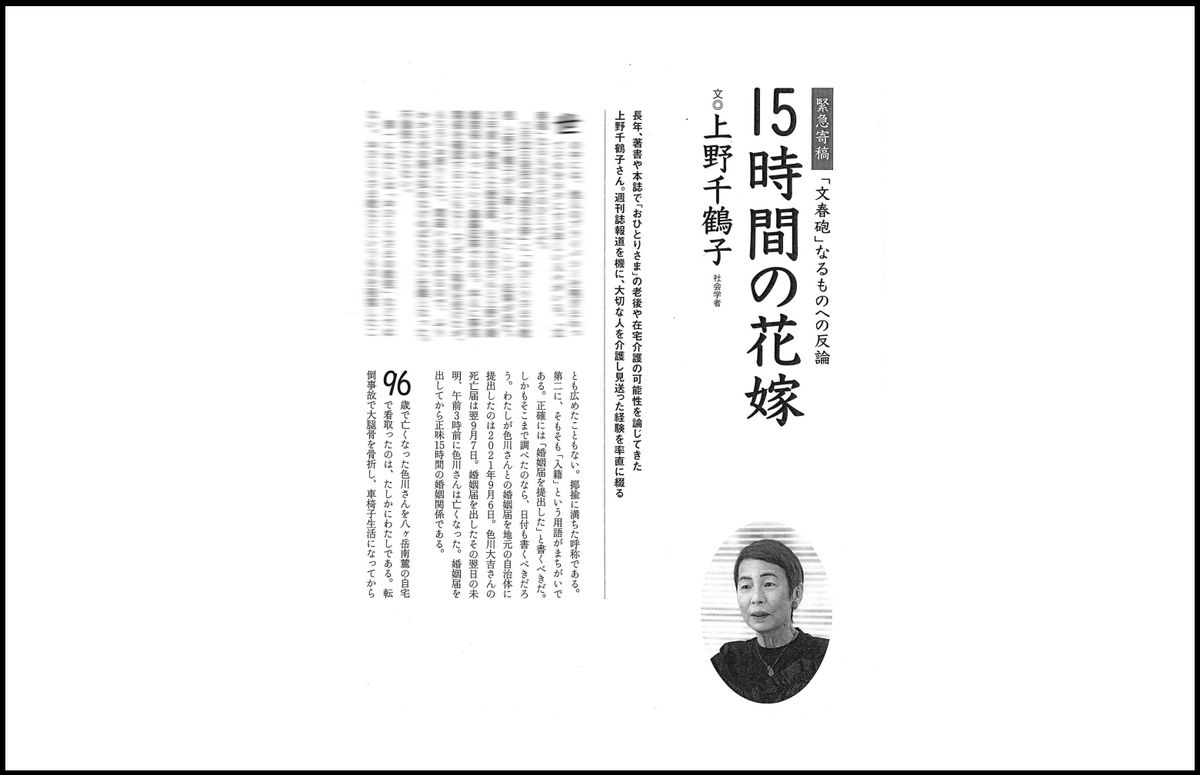
文春報道が出た際に「入籍」とは婚姻なのか養子縁組なのか?という疑問が出ていました。それについて上野氏は婦人公論2023年4月号で「婚姻届を提出した」と言っていました。
結果的に婚姻届を提出してから15時間後に色川氏が亡くなったようです。
法的婚姻関係を偽装する婚姻届の提出=婚姻意思の不存在=無効自由
上野氏は婦人公論で「そもそも「入籍」という用語が間違いである。正確には「婚姻届を提出した」と書くべきだ」「各種の手続や相続に家族が優先されることは骨の髄まで染みついていた」「家族主義の日本の法律を逆手にとるしかないと思い至った」「手段はふたつあった。養子縁組か婚姻か」「色川さんが第三者にわたしを紹介してくれるときのいちばんうれしい言い方はこうだった。「このひとはボクの親友です」」と書いています。
つまり、「婚姻の法的効果を享受する目的」で婚姻をしたのであって、その先に夫婦としての共同生活を送る目的が感じられない。もちろん上野氏の言うような「セックス契約」の意思も感じられない。
これは「婚姻意思の不存在」を証明する事情であり、上野氏と色川氏の婚姻は、本来的には無効と法的には評価されるものと言えます。判例の規範は以下です。
民法
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
最高裁判所第二小法廷判決 昭和44年10月31日 昭和42(オ)1108 民集第23巻10号1894頁
所論は、民法七四二条一号にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、法律上の夫婦という身分関係を当事者間に設定しようとする意思がない場合と解すべきである旨主張する。
しかし、右にいう「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものと解すべきであり、したがつてたとえ婚姻の届出自体について当事者間に意思の合致があり、ひいて当事者間に、一応、所論法律上の夫婦という身分関係を設定する意思はあつたと認めうる場合であつても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであつて、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意思がなかつた場合には、婚姻はその効力を生じないものと解すべきである。
その上で、最高裁のこの事例では子に嫡出子としての地位を得させるための便法として婚姻の届出をしたことについて無効とされました。
上野氏の場合も、①届出意思と②法律関係設定意思は上野・色川両氏にはあったが、③夫婦生活意思は両氏共に存在していないので(介護生活という外形的事実はあるが)、本来的には無効となります。
特別縁故者としての上野千鶴子と親族からの婚姻無効訴訟の可能性は?
上野氏によれば色川氏の息子を含めた親族は上野氏が色川氏を介護することについて承知していたようです。
が、「婚姻をして相続すること」について色川氏の親族がどう考えていたのかは、書かれていません。
ただ、介護期間中に資産管理・預貯金解約・口座をひとつにまとめるなどの手続をしていたことから親族も容認していた可能性がありますから、「色川氏のその他親族が相続に関して婚姻無効を主張する」という争いが生じることは今のところはなさそうですが…
※仮に無効が主張された場合でも、婚姻の届出をすることを容認していたのであれば、上野氏が介護生活を取り仕切っていたことなどから無効の主張をすることが信義則違反で制限される可能性はあるのかもしれないが
もっとも、上野氏の採った方法を一般化するのは危険だと思います。
仮定的な状況として、死亡者に相続人が居らず、相続債権者及び受遺者も特別縁故者も居ない場合、財産は国庫に帰属することになります。
その状況で婚姻意思の不存在となる婚姻の届出で相続財産を得た場合、それは国家の財物となるはずであったものを詐取したとはならないのか?という疑問が出て来ます。
※遺贈では課される相続税が相続では回避される可能性がある
上野氏の場合は仕事場を移してまで色川氏の介護生活を支援していたため、婚姻をしておらず相続人とされなくとも「特別縁故者」と認定されるでしょう。
が、それでも相続人としての地位によって相続できるものと、特別縁故者として家庭裁判所に請求して得ることのできる清算後の相続財産とでは本来的に範囲が異なるため、「いずれにしても特別縁故者だから良いだろう」となるでしょうか?
本件では①届出意思と②法律関係設定意思は色川氏も有していたようであり、色川氏の意向を無視して強引に婚姻関係が法的に設定された事案でもないから、仮定的な状況であっても立件するのはどうなんでしょうか?
こうした特殊状況を無視して「身寄りのない人間が死亡する前に婚姻届を出してしまえば問題なく相続できる」とするのは、危険のような気がします。
なお、相手方の意思がないのに婚姻届けを偽造して提出したら有印私文書偽造等罪などに問われます。
以上:はてなブックマーク,ブログ,note等でのご紹介をお願いします

