朝日新聞デジタルにおいて、横大道聡(よこだいどうさとし)教授が「トリエンナーレ表現の不自由展の事案は表現の自由の侵害であるとするには困難」と指摘しました。
トリエンナーレ表現の不自由展に横大道聡教授『「表現の自由の侵害」は困難」
憲法学者が考える不自由展中止 自由を制約したのは誰か:朝日新聞デジタル
あいちトリエンナーレの企画展「表現の不自由展・その後」が中止に追い込まれた。憲法が保障する「表現の自由」の問題として考えた時に、どのような意味があるのか。行政による文化芸術活動への助成に詳しい慶応大学の横大道聡(よこだいどうさとし)教授(憲法学)に聞いた。
中略
「もともと表現の自由は、戦前のように政府批判をしたら逮捕されるなど、あからさまでわかりやすい圧力を想定したものでした。基本的な発想は、刑事罰などによって、表現活動を妨げられないということです。一方で表現の自由は、発表の機会を提供したり、作品を購入・展示したりすることまで、行政に義務付けるものではないというのが、判例や憲法学の通説的な理解です。そのため、不自由展を担当した実行委員会や展示作品の作者の『表現の自由』の問題であるとする議論の立て方は、少なくとも裁判では、簡単には通用しないと思います。自分のお金・時間・場所で同じ表現を行うことは何も規制されていないからです。誰かがお金を出さない、場所を貸さないなどの微妙なやり方で表現の自由に対して影響を与えようとしてきたとき、それを直ちに表現の自由の侵害ということは困難を伴います」
このような発想は憲法学界の通説的認識です。
アメリカの連邦最高裁の判例でも、類似の事例において「政府言論であるために表現の自由の問題ではない」と一蹴したものがあります。
日本においてトリエンナーレの類似事例が裁判になったことが無いので、好き勝手に言ってる人が居るというだけの話です。
横大道聡教授 「公的言論助成に対する憲法的統制の在り方についての一考察」
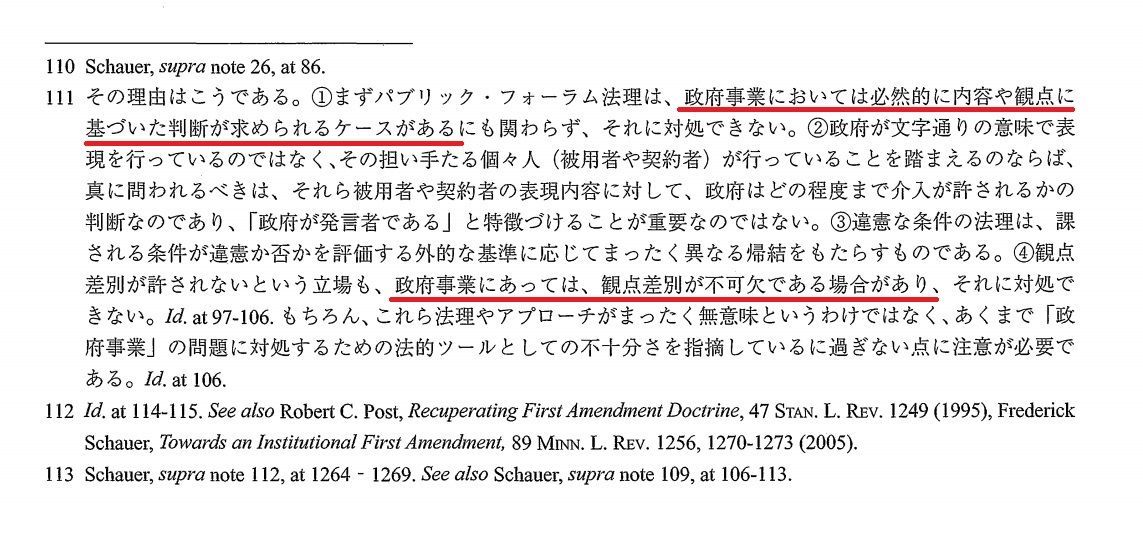
鹿児島大学リポジトリ(公言論助成に対する憲法的統制の在り方についての一考察)
横大道聡教授の表現の自由に関する見解についてネットで見れるものとしては上記論文があります。
上記は注の説明ですが、アメリカ憲法学界では「政府事業・政府言論」には必然的に内容や観点に基づいた別異取扱いがあり得るという認識が前提としてあるということ、政府の行為と民間人の行為とは一応分けて考えられているということが分かります。
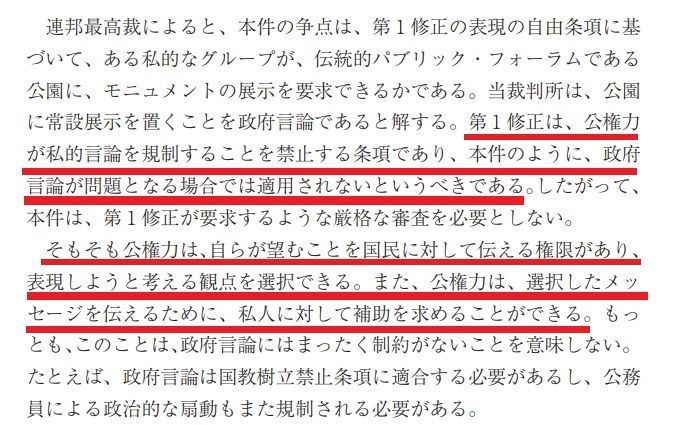
政府の言論と人権理論 (3) 金澤, 誠 北大法学論集, 61(5), 144[65]-81[128]
政府言論について真正面から論じているのが金澤教授の論文。
アメリカの市が管理する公園において、ある宗教団体がモニュメントの展示を求めたが、市が認めなかったことが表現の自由条項違反だとして争われました。
連邦地裁は表現の自由の話だとしましたが、連邦最高裁は公園の展示は「政府言論」(ガバメントスピーチ)であるとして、その場合は表現の自由条項の問題ではないと判断しました。
トリエンナーレは実行委員会がほぼ愛知県の事業であるので、「政府事業・政府言論」に当たり、表現の自由の問題ではないとされる可能性が高い事案なのです。
もちろん、日本においてアメリカと同じ論法が取られるのかは不明ですから、表現の自由の問題であると言うことが間違いだと言い切ることもできませんが、原則的には苦しい主張になるという状況があります。
朝日新聞は紙面では掲載せず
横大道教授へのインタビューは14日の朝日新聞デジタルでは掲載されていますが、14~16日の紙面では掲載されていません。
この問題が起こってから朝日新聞は「憲法上の検閲」などとトンチンカンなことを書いていたので、横大道教授の発言を紙面で読者に見せるのは嫌なのでしょう。
以上
